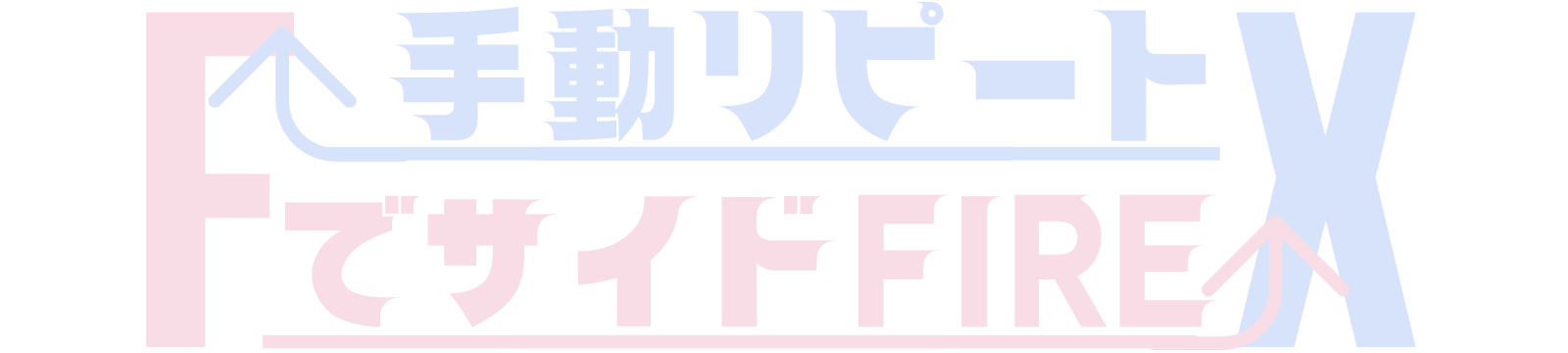このブログは以前は「鈴さんのトラリピでセミリタイアするのは無理ゲー」というタイトルでした。
しかし、セミリタイアできた人なんて結局ほとんどいなかったし、むしろ大損している人ばかりが目立ちます。
残念ながら失敗した人が何人か出てきてしまいました・・・
トラリピ188週目にして、ロスカットしました#トラリピ #トラリピ鈴 pic.twitter.com/VRadIzdaVN
— やすひろ👛へそくり運用 (@yasuhiro8686) April 11, 2024
#トラリピ 全損切・撤退しました。
— すぜ~@不労所得生活目指し中 (@yshimjp2001) April 15, 2024
維持率115%を割ったので、
思い切って全部取り消しました。残念です。
トータル入金700万円で戻りが118万円、
税金考慮するとマイナス600万円です。
FXは懲りました。他で取り戻せるよう頑張ります。 pic.twitter.com/IMfxbI3hcg
トラリピ、撤退します😭
— かほ@自由への一歩 (@kaho_jiyu) April 21, 2024
証拠金維持率が230%あたりで大きくばっさり切って、今はプラススワップのつくポジョンだけを残しています。
それもどうするか考え中🙄
残ったお金は新NISAの資金にします。
しばらくは心がぽっかりでしたが、やっと自分の中で整理がつき始めたところです😅#トラリピ pic.twitter.com/azlqfOgdxR
トラリピの運用をはじめてたった3年でセミリタイアを達成してしまった鈴さん本人に対して、マネした人はどうしてこんなに成績が悪いのでしょう?
このブログではそのカラクリを暴露していきます。
鈴さん本人は本当にトラリピでセミリタイアしたの?

その答えは「はい」であり、また「いいえ」でもあります。
要は確実にトラリピでセミリタイアしたと言い切れるものではなく、捉え方によって答えがかわります。
なお投資の成績は正しく報告している
鈴さんは、これまでFXのトラリピを筆頭にいろいろな投資で利益をあげ続けてきました。
証明まではできませんが、公開している数字もこと細かいし矛盾もないのできっとすべて正しいものでしょう。
さらに口座のスクショを載せていることもあるので、投資の成績は正確だと判断できます。
では、トラリピでセミリタイアしたと言い切れない理由は?
鈴さんのブログでは総資産がクローズアップされています。
その総資産額を見ると、セミリタイアした2018年時点でもブログ収益で稼いだ割合が圧倒的に多いのです。
さらに2024年夏現在では、なんと投資の総合成績(時価総額ベース)は赤字なのです。
もちろんトラリピの総合成績も赤字です。
トラリピでセミリタイアしたと本人は言っていますが、この内容を見るとなんか騙されているような気分になるのはわたしだけでしょうか?
つまり鈴さん本人しか収益が上がらないのでマネすべきではない
上記の現象をぶっちゃけて言うとこうなります。
トラリピはダメでブログ収益でしか稼げてないからマネした人の多くは損をする
ここで、「ちょっと待ってよ」と思った方、するどいです。
なぜなら鈴さんのワイドレンジのトラリピは今でもしっかり黒字だからです。
公開運用の成績が黒字なのに損をするなんていちゃもんつけてるのか?
そう思った方は続きを読んでみてください。
ワイドレンジは相場を読まない手法

鈴さんのメイン手法であるワイドレンジのトラリピは、本人が何度も述べているように「相場を読まない」手法です。
そこに、ある日「円安シフト」という相場観を入れた運用を混ぜたのです。
相場観のないワイドレンジの成績が悪い証拠としては、ワイドレンジ積み立てバージョンがあります。
こちらは「円安シフト」を取り入れなかったので資金が半分程度にまで目減りする大赤字になっています(2024年夏時点)
つまり、この円安シフトをマネした人だけは、鈴さんのトラリピをマネしていても未だに黒字の可能性があります。
なお、この円安シフトも手放しで褒められたものではありません。
その理由が2つあるので、順を追って説明していきます。
円安シフトの問題① フルでマネできる人が少なかった

円安シフト自体はとても効果的でした
ただ、これをフルでマネできる条件が非常に難しくほとんどの人には不可能でした。
それは円安シフトが2022年春という特定のタイミングで行われたからです。
つまり、これより前から鈴さんのトラリピをマネしている人しか円安シフトはできませんでした。
さらに、円安シフトはその当時クロス円の赤字売りポジションを持っていれば持っているほど効果が高い方法でした。
鈴さん本人よりクロス円の赤字売りポジションを当時持っている人はいなかったはずなので、本人以外にとっては効果はかなり限定的でした。
円安シフト問題② ただの裁量トレード

円安シフトは成功しましたが、はっきり言うとたまたまトレードが成功しただけです。
ですから再現性がなく本来は参考にできるものではありません。
先ほどから円安シフトのような取引を相場観のあるトラリピと呼んでいますが、実は鈴さんは円安シフト以外にもこの相場観のあるトラリピをしています。
それがナローレンジと呼ばれるトラリピです。
こちらの成績を見ると目も当てられない惨劇となっています。
つまりどういうこと?

つまり鈴さんのトラリピをマネして利益を出すのは難しいということです。
もちろん利益を出している方もいますが、割合で言えば少数だと推測され、過半数が利益を出せるわけではないのです。

ちなみにわたしはアンケートで利益を出している方の割合の把握に努めています

鈴さんはむしろそういうことを知りたくない(知られたくない)雰囲気あるよね
1番のメイン手法であるワイドレンジのトラリピでは一見すると利益が出ているように見えます。
ただそれは円安シフトという鈴さんの相場観を入れた方法が成功しただけで、相場観なしの本来のワイドレンジだけ取り出すと大赤字です。
では鈴さんの相場観にのれば利益が出せるのでは?
このように思う方もいるかもしれませんが、どうやらたまたま円安シフトだけが成功したと考えた方がよさそうです。
なぜなら相場観ありのトラリピを公言しているナローレンジ手法では、とんでもなく悪い成績になっているからです。
つまり相場観なしのワイドレンジでもダメ、相場観ありのナローレンジでも失敗
これが鈴さんの2024年夏時点でのトラリピの成績です。
ただブログ収益だけは非常に優秀でこれまで合計で2.5億円近くの収入を得ています。
むしろこれだけブログ収益があれば、いまのように投資がかなり失敗していてもセミリタイアはできます。
鈴さんのトラリピに成功やセミリタイアの夢を見た人には申し訳ありませんが、これが悲しい現実なのです。
鈴さんは意図的に悪気があって情報発信を継続しているわけではないとは思います。
それでも、もしブログ収益がなかったらセミリタイアは継続できず働かないとやっていけない状況なのは事実です。
つまり、これまでのブログ収益や過去のある時点までの投資成績がよかっただけなのです。
その後はひどい成績が続いているので、参考にするのは危険だと思います。